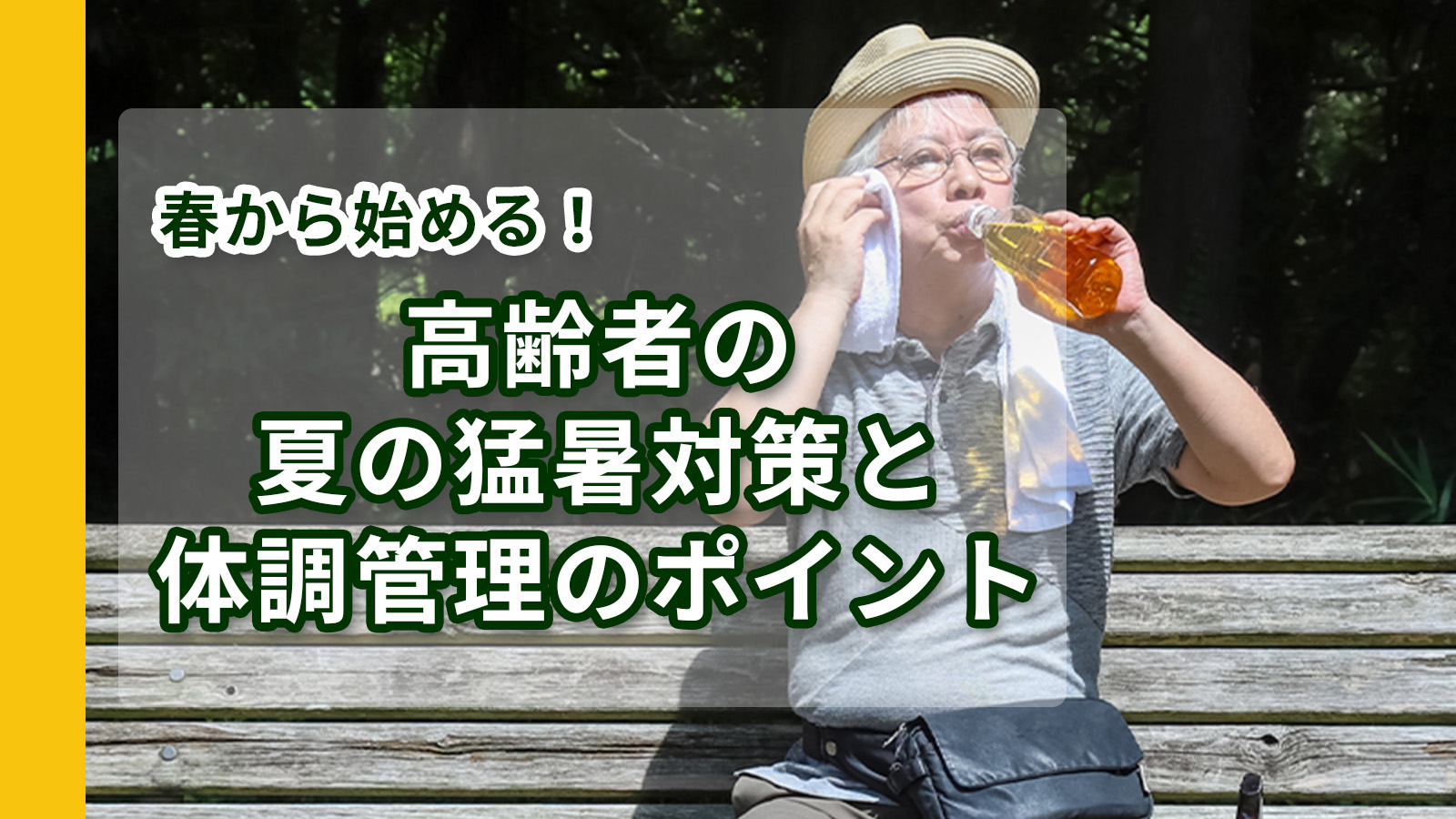
「夏の暑さは年々厳しくなっているように感じるけど、今年も無事に過ごせるかしら……」
そう不安に思う方は少なくありません。特に介護を必要とする高齢のご家族を抱える場合、熱中症や夏バテの危険性はさらに大きな関心事となるでしょう。
実際、熱中症で救急搬送された高齢者の割合は非常に高く、厚生労働省の調査によると、熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。このため、高齢者は特に注意が必要です。
参考:熱中症を防ぐために知っておきたいこと~熱中症予防のための情報・資料サイト|厚生労働省
しかし、高齢者の暑さ対策は、暑くなってから始めるのでは遅いことがあります。むしろ、春のうちから少しずつ準備を始めることで、猛暑を迎える頃には万全の体勢が整い、安心して夏を乗り切ることができるのです。
本記事では、「高齢者が夏に弱い理由」を踏まえながら、具体的な暑さ対策や体調管理のポイントを分かりやすくご紹介します。日頃の介護の中で簡単に取り入れられる工夫を中心にお伝えしますので、ぜひご家族が協力して、無理のない範囲で取り組んでみてください。読み終えたあとには、「今年の夏も快適に過ごせそうだ!」と前向きな気持ちになっていただけるはずです。
高齢者が夏に弱い理由とは?

「高齢者は暑さに弱い」と言われるのは、単に体力が落ちるからだけではありません。高齢の方々は体温を調節する機能そのものが低下しやすいため、若い世代に比べて熱中症や夏バテを引き起こしやすいのです。さらに、持病や服薬の影響も加わることで、体内の水分量が不足しやすくなるリスクも高まります。
参考:熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて|厚生労働省
理由1:体温調節機能の低下
人間の体は、気温が上昇すると発汗や皮膚の血管拡張によって体温を下げる働きをします。しかし、高齢者は汗腺が減少・機能低下していたり、血液循環が弱まっていたりするため、若い頃のように効率よく体温を下げられません。
例えば真夏日が続くとき、若い人なら汗をかいて体温を外に逃がせるところ、高齢者は汗の出が追いつかず体内に熱がこもりがちになります。その結果、本人も「それほど暑くない」と感じていても実際には体温が上昇し、熱中症リスクが高まるのです。
理由2:水分不足と脱水リスク
高齢者が暑さに弱いもう一つの理由が、水分不足と脱水リスクの高さです。歳を重ねると喉の渇きを感じにくくなったり、トイレが近くなるのを嫌って水分補給を控える傾向が強まったりする場合があります。
また、心疾患や腎疾患などで利尿剤を服用している方は、汗をかく以前に尿として水分が排出されやすくなるため、体全体の水分量が不足しやすくなります。水分が不足すると血液循環が滞りやすくなり、体温調節機能の低下が一層進むという悪循環にも陥りがちです。
春から始める「高齢者の猛暑対策」

いざ真夏になってから「暑いから対策をしよう」と考えても、冷房機器の調子が悪かったり、生活習慣が定着していなかったりすると、思うように対策が進みません。そこで大切なのが「春のうちから少しずつ準備を進める」という視点です。
以下では、猛暑を迎える前に着手しておきたい対策をいくつかご紹介します。できるものから始めてみてください。
対策1: 室内環境のチェックと整備
エアコンの試運転・点検: 夏本番になると修理・買い替えの依頼が集中し、業者の予約が取りづらくなります。フィルターの掃除や試運転を春のうちに行い、異常がないか確かめておきましょう。
参考:夏季を迎える前のエアコン試運転の重要性について|経済産業省
遮熱・断熱対策の確認: 直射日光を和らげるために、すだれや遮光カーテンの準備を早めに行うこともポイントです。東西に向いた窓がある場合は、朝日や夕日が入りやすい時間帯を狙って、カーテンやブラインドでしっかり日射を防ぎましょう。
対策2:水分補給の習慣づくり
気温が高くなる前から、こまめに水分を摂る習慣づけを始めましょう。高齢者は喉の渇きを自覚しにくいため、のどが渇いていなくても定期的に水分補給するよう声かけをします。厚生労働省の資料でも「のどが渇かなくても、早め早めに水分や塩分を補給しましょう」と呼びかけられています。
暑さが本格化してから「こまめに水を飲んで」と言っても、本人の意識がついていかない場合があります。そこで、比較的涼しく過ごしやすい春の時期から、たとえば「朝食後に1杯」「昼食後に1杯」「おやつの時間に1杯」というように、決まったタイミングで水分を取る習慣を一緒に作っていきましょう。
対策3:栄養バランスの見直し
夏バテ対策の食事: 加齢とともに食が細くなりやすい高齢者こそ、春から栄養バランスに配慮した食事を続けることが重要です。タンパク質やビタミンB1・C、ミネラル(ナトリウム・カリウムなど)をしっかり摂取できるよう、日々の献立を工夫してみましょう。
冷たいものばかりに偏らない: 暑いと冷たい飲み物や麺類に偏りがちですが、体力を落とさないよう、汁物や煮物など温かいメニューも適度に取り入れると良いでしょう。こうしたメニューは水分や塩分補給にも役立ちます。
対策4:春~初夏の衣替えで涼しさを意識
暖かくなってきたら高齢者の普段の服装もチェックしましょう。通気性が良く吸湿速乾性のある素材の衣服は、汗をかいても蒸れにくく体温を逃しやすくなります。
通気性の良い素材を選ぶ: 木綿や麻など吸湿性・速乾性がある素材の衣服を増やし、締め付けの少ない靴下や下着を準備しておくと、真夏になっても快適に過ごせます。
室内着も涼感重視: 室内で過ごす時間が長い高齢者ほど、部屋着が快適さを大きく左右します。軽くて風通しの良い素材を取り入れてみてください。
高齢者の熱中症・夏バテを防ぐ具体策

春の準備が整ったら、いよいよ夏本番に向けた実践に入ります。高齢者の熱中症や夏バテを防ぐには、夏場の室温管理や屋外活動時の注意点など、いくつかのポイントを押さえることが大切です。ここからは、その具体的な取り組み方について順を追って解説します。
具体策1:エアコンの適切な利用
エアコンの適切な利用は、室内の温度管理を通じて熱中症を予防するうえで最も重要なポイントとなります。室温が28℃を超えるようなら迷わず冷房を使用し、約28℃を目安に室温を維持することを心がけましょう。
参考:熱中症、こんな人は特に注意!|一般財団法人 日本気象協会
高齢者は部屋の暑さを感覚で把握しづらいため、温度計や湿度計で客観的にチェックすると安心です。また、エアコンの風を嫌がる場合は、風向きを調整して直接肌に当たらないようにしたり、扇風機で室内の空気を循環させたりする工夫が効果的です。そうすることで冷房の不快感を和らげつつ部屋全体を涼しく保てます。「自分は暑くない」とエアコン使用を渋る方には、室温が高いと健康に大きなリスクがあることを丁寧に説明し、短時間だけでも冷房をつける大切さを理解してもらうことが大切です。
具体策2:屋外活動時の注意点
夏場に高齢者を外に連れ出す場合、時間帯と暑さ対策に注意を払います。炎天下の外出はできるだけ避け、特に正午前後の気温が最も高くなる時間帯には無理をしないようにしましょう。もし日中に外出が必要なときは、日傘や帽子を着用し、適宜日陰で休憩を取りながら、水分補給することがおすすめです。
日本気象協会の「熱中症警戒アラート」など暑さ指数(WBGT)の情報を参考に、危険な暑さの日は外出を控えるという判断も視野に入れてください。
また、外出時は必ず水筒などに飲み物(できれば経口補水液やスポーツドリンク)を携帯し、こまめに水分と塩分を補給できるようにします。服装は吸汗速乾の長袖シャツや日除け効果のある薄手の上着を羽織るなど、直射日光から皮膚を守る工夫をしながら通気性も確保するとよいでしょう。
具体策3:快適な睡眠環境の工夫
快適な睡眠環境を整えることも、夜間の熱中症や夏バテを防ぐために重要な対策です。暑い日中に熱せられた室内は、夜になっても壁や天井にこもった熱のため気温が下がりにくくなります。就寝前には窓開けや扇風機を使ってしっかり換気を行い、必要に応じてエアコンで寝室を適切な温度まで冷やしておきましょう。
あわせて通気性の良い寝具や冷感素材のシーツ・パッドを利用し、汗をかいてもベタつきにくい寝床を整えると、寝苦しさが軽減されて睡眠の質が維持されます。十分な休息は体力の回復につながり、夏バテを遠ざける大きな要因となるでしょう。
介護する家族が気をつけるべきこと

猛暑時期、高齢者本人の対策だけでなく、介護するご家族が常に気を配ることも大切です。以下に、介護者が特に注意したいポイントをまとめます。
1:こまめな体調チェック
こまめな体調チェックは毎日のケアの中で欠かせない取り組みです。高齢者の体調に些細な変化がないか観察する習慣を持ちましょう。たとえば「元気がない」「食欲が落ちている」「微熱がある」「腋の下や口の中が渇いている」といった症状が見られないか確認し、血圧や脈拍の変動にも留意します。
異常があれば早めに休息をとらせたり、涼しい環境に移すといった対応を取りましょう。脱水の兆候があれば熱中症の前触れである可能性もあるため、早期に対処することが重症化防止につながります。
2:水分補給のチェック
脱水症や熱中症を防ぐには、1日に必要な水分をしっかり摂取することが欠かせません。高齢者の場合、最低でも1日に1,500mlの水を取る必要があると言われています。
そのため、目安としては1日1,500~1,800ml程度を目標にし、飲み忘れや飲む量が不足しがちになっていないか、家族がときどき確認しましょう。飲みやすい温度のお茶や水、経口補水液などを少量ずつこまめに飲めるよう、キッチンやリビングなど目につきやすい場所に準備しておくと効果的です。
ただし、高血圧や心不全、腎臓病などで医師から水分制限の指示を受けている場合は、主治医の指導に従うようにしてください。












