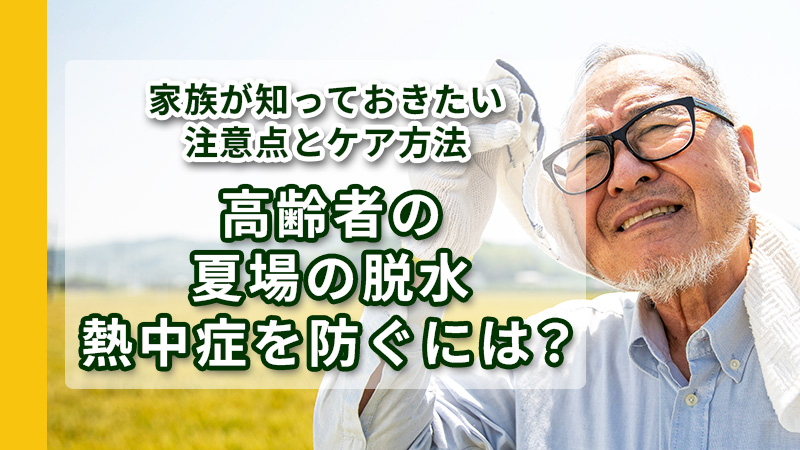
近年の厳しい暑さの影響から、高齢者が熱中症や脱水に陥るケースが増えています。特に、室内にいる高齢者が亡くなるケースも増えており、安心して過ごすためにも、熱中症や脱水への備えが欠かせなくなっています。
本記事では、高齢者が夏場の脱水や熱中症になりやすい理由から、各段階の症状やケア方法、日々の予防法まで詳しく解説します。高齢家族と離れている方はもちろん、同居している方 も、脱水・熱中症対策にご活用ください。
高齢者が夏に熱中症・脱水になりやすい理由

高齢者は、若年者よりも熱中症や脱水症になるリスクが高いといわれています。ここでは、その理由について詳しく解説します。
体温調整機能の低下
人の体は周囲の温度や環境に合わせて常に体温を調節していますが、高齢になると以下の理由で体温調節機能が低下します。
筋肉量の減少による影響:
筋肉には多くの水分が含まれているため、筋肉量が減少すると体内の水分量も減少します。また、筋肉量の減少は基礎代謝の低下につながり、体温の維持が困難になります。
皮膚感覚の変化:
皮膚の感覚が鈍くなると、特に暑さを感じにくくなります。室温の上昇に気づかなかったり、体温調節が適切に行われなくなったりします。その結果、室内が暑くても不快に思わず、エ アコンなどを使わなくなるため、熱中症や脱水症に陥りやすくなります。
水分摂取の減少とサインが見えにくい理由
高齢者が脱水に陥りやすい理由は、水分摂取量の減少だけでなく、脱水症状のサインを感じにくいことにもあります。
- 口渇感の低下:のどの渇きを感じにくい
- トイレを我慢する心理:頻尿や失禁、夜間のトイレを気にして水分摂取を控える
- 嚥下機能の変化:誤嚥を恐れて食事や水分を摂取量が少なくなる
服薬の影響:薬に含まれる利尿作用によって、水分排出を増大している
これらの要因が複合的に作用することで、高齢者は知らず知らずのうちに「かくれ脱水」の状態に陥りやすく、のどの渇きに気づいたときには重症化していることもあります。
こんな症状が出たら要注意!熱中症・脱水の初期サイン

熱中症や脱水症の症状は多岐にわたる一方、時間とともに生命にかかわる状態へと重症化していきます。早期発見・早期ケアをするために、注意が必要な症状・サインを解説します。
軽度~重度の症状を段階別に
熱中症・脱水症の症状は段階的に現れます。軽度な初期症状の段階で対処することで、深刻な状態への進行を食い止めることが大切です。
軽度(I度):意識ははっきりしている
- めまい、立ちくらみ
- 筋肉のこむら返り(足がつる)
- 手足のしびれ
- 頭痛、吐き気
中度(II度):意識はあるが、呼びかけに対する反応がおかしい
- 頭痛、吐き気、嘔吐
- 全身の倦怠感
- 体の引きつり(けいれん)
血圧の低下
重度(III度):意識がない、呼びかけに反応がない
- 高体温(40℃以上)
- まっすぐ歩けない・走れない
- けいれん
- 体が熱い
軽度の症状では、まだ生命の危険は少ないものの、ふらつきや立ちくらみによる転倒リスクがあるため、まずは安全な場所に座らせることが重要です。
中度以上の症状が現れている場合は医療機関での治療が必要です。患者の状況に応じて、家族が病院へ連れて行くか、救急搬送を判断し、一刻も早く医療機関を受診しましょう。
見守る家族が気付くポイント
高齢者自身は暑さやのどの渇きに気づきにくく、初期症状が出ていても深刻な状態だと認識していないことがあります。そのため、見守っている家族が日頃から注意深く観察することが、熱中症・脱水症の予防・早期発見に非常に重要です。
観察できる具体的な身体的サインには、主に次のようなものがあります。
- 普段と比べて元気がない
- 食欲がない
- 口数が少ない
- 反応が鈍い
発熱がある
皮膚の状態
- 皮膚が乾燥してカサつく
- 唇や舌が乾いている
- 脇の下が湿っていない
- 手の甲の皮膚をつまんで3秒以上戻らない
尿の状態
- 排尿の回数や量が少ない
- 尿の色が濃い、茶色い
その他の変化
- 急激な体重減少
- いつもよりぼーっとしている
- うとうとと傾眠傾向になる
これらの変化が見られたときは、室温や体温、水分摂取量を確認し、熱中症・脱水症が起きていないか慎重に判断しましょう。
熱中症・脱水に気づいたら
熱中症・脱水症の可能性が高いと判断したら、すぐに適切な応急処置を行うことが重要です。ここでは、重症化を抑え、命を守るための応急処置方法を解説するので、焦らずに対応でき るようあらかじめ確認しておきましょう。
基本的な応急処置の手順
熱中症・脱水の基本的な応急処置は、基本的に以下の3つのステップで行います。
- 涼しい場所への移動
風通しの良い日陰や、エアコンが効いた室内へ移動します。
- 衣類を緩める
ベルトを外すなど、衣類を緩めて安静に過ごせる体勢で座らせるか、寝かせます。
- 体を冷やす
濡れタオルや氷、アイスパックで体を冷やします。
体を冷やすときは、太い血管が通っている、以下の部分を重点的に冷やしましょう。
- 首筋の両側
- 脇の下
- 足の付け根(鼠径部)
これらの部位に濡れタオルや氷を優先して置くようにすると、素早く体を冷やせるため、効率的に熱中症・脱水の進行を抑えられます。
症状の程度に応じた対処法・注意点
基本の応急処置は、どの段階でも有効ですが、症状が重くなると病院での早期治療が必要です。そこで、基本の応急処置をふまえ、症状の程度ごとに最適な方法で対処できるようになりましょう。
- 軽度の症状:経口補水液などを使って水分と塩分を補給します。症状に改善が見られる場合は、そのまま安静に休ませます。
- 中度の症状:水分を自分で飲ませると誤嚥の危険があります。スプーンなどで少しずつ与えるようにして、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 重度の症状:処置を行う前に迷わず救急車を呼びましょう。救急車が到着するまでの間に、涼しい場所への移動や体を冷やす処置を行い、重症化を防ぎます。
家族ができる日常ケアと予防の工夫

高齢者の熱中症・脱水は、生活習慣の工夫・改善によって、ある程度予防できます。ここでは、熱中症・脱水の予防に効果的な対策を紹介します。
水分補給のタイミングと種類(コーヒー・お茶はOK?)
のどの渇きを感じにくい高齢者にとって、自分で水分管理をするのは困難です。時間を決めて定期的に水分を摂る習慣を作りましょう。
1日の水分量の目安は1.2リットル(コップ約6杯分)です。起床時、朝食時、午前10時、昼食時、午後3時、夕食時、入浴前後、就寝前など、各タイミングでコップ1杯程度の水分摂取を習慣化しましょう。
日中の飲み物は水やお茶など、一般的なもので問題ありません。冷蔵庫で冷やしたものは、 吸収がよく体温の冷却効果も期待できるため、なるべく冷えたものがおすすめです。ただし、コーヒーや緑茶は利尿作用のあるカフェインを含んでいるため、水分補給という点では適していないので注意が必要です。
また、嚥下障害などで水分を飲み込むことが難しい場合は、市販の水分補給用のゼリー飲料や、とろみをつけた飲み物を活用しましょう。フルーツやゼリー、スープなど、食事からも水分を摂る工夫も有効です。
冷房・衣類・食事でできる対策
室内や夜間でも熱中症・脱水は多く発生しています。そこで、冷房、衣類、食事の3つのポイントから、実践しやすい対策を紹介します。
冷房対策:
室温が28℃を超えたらエアコンをつけるなど、明確なルールを決めましょう。部屋に温湿度計を設置して、室温をこまめにチェックしながら、快適な室温に調整することが重要です。
衣類の工夫:
軽装を心がけ、以下のような点を意識して選びましょう。
- 吸汗性・速乾性がある
- 透湿性・通気性が良い
- 冷感素材
- ひとりで脱ぎ着しやすい
食事での対策:
水分を多く含む夏野菜や果物、汁物などを積極的に取り入れましょう。食事の栄養バランスにも気を配り、食事から筋肉の維持や体力向上を目指すことも大切です。
無理な運動を避ける!安全な運動法とは
筋肉量の低下は、熱中症・脱水になりやすくなる要因の1つです。そこで、日頃から体を動かして筋肉量を維持することも大切です。ただし、熱中症予防運動指針では、温高温・高湿度の環境での運動は熱中症・脱水症のリスクが非常に高いです。なるべく涼しい屋内で体を動かしましょう。
筋肉量の維持に有効な運動には、次のようなものがあります。
- 両腕前方伸ばし(肩と背中のストレッチ)
- 上方背伸び(肩と体側のストレッチ)
- 両脚上げ(腹筋と脚付け根の筋トレ)
- スクワット(太ももの筋トレ)
下にいくほど負荷が高くなり、スクワット以外は座って行えます。筋力に不安がある方は上の運動から実践し、決して無理をしない範囲で体を動かしましょう。
まとめ|「ちょっとした変化」に気づけるのは家族だけ

高齢者の熱中症や脱水症は、本人が気づかないうちに進行し、気づいたときには生命に関わる深刻な状態であることもあります。そのため、高齢者の熱中症や脱水症の早期発見には、身近にいる家族や介護者の存在が欠かせません。
まずは、日常的に高齢者の様子を注意深く観察することが大切です。「いつもより口数が少ない」「顔色が悪い」といった小さな変化が、脱水症や熱中症の初期兆候である可能性があります。
また、家族からの積極的な声かけは、高齢者の健康管理に非常に有効です。「大丈夫?」「何か飲む?」といった一言が、体調不良の早期発見や水分補給の促進につながります。
「ちょっとした変化への気づき」と「積極的な声かけ」の2つを意識して実践し、大切な家族の健康を守りましょう。
SONOSAKI LIFEでは、健康づくりに役立つ情報や介護の「お悩み」に寄り添う情報をお届けしております。 他のコラムもぜひ、ご覧ください。










