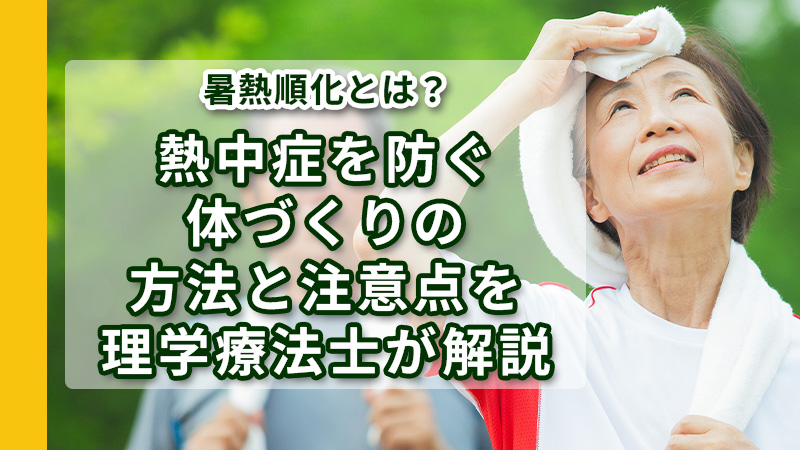
夏になると毎年のように耳にする「熱中症」。実は、気温が急に上がる初夏や梅雨明け、そしてお盆明けのタイミングで発症が増える傾向にあります。その大きな理由のひとつが、まだ体が暑さに慣れていないこと。
この暑さに慣れる仕組みを「暑熱順化(しょねつじゅんか)」と呼びます。
暑熱順化は、気温の上昇に体を適応させる大切な生理的プロセスです。とくに高齢者や子ども、運動習慣がない方は、暑熱順化の影響を受けやすく、正しい知識と対策が欠かせません。
この記事では、暑熱順化の方法と注意点や、身体機能との関連を理学療法士の視点で紐解きます。
暑熱順化とは?

人間の身体は、暑さにさらされることで少しずつ対応力を高めていく機能を持っています。これが「暑熱順化」であり、具体的には次のような変化が起こります。
これらの変化によって、熱中症になりにくい身体が作られます。
暑熱順化にかかる時間は、おおよそ5日から2週間程度が目安です。ただし、その効果は継続的に汗をかくような生活をしないと数日で失われるため、日常的な取り組みが大切です。
暑熱順化が必要な理由

熱中症は、気温だけでなく身体の状態にも大きく左右されます。とくに体温調節機能が未熟な子どもや、衰えている高齢者では、暑さに対して敏感でなくなっていることが多く、順化が遅れやすくなっています。
さらに、最近は在宅時間の増加や空調の効いた室内生活が多く、外気に触れる機会が減少。そのため、いざ外出すると身体が対応できずに体調を崩してしまう…というケースも増えています。
介護をされている方やアクティブなシニア層にも、暑熱順化は「自分を守る」だけでなく「大切な人を守る」ためにも、ぜひ意識して取り入れていただきたい習慣です。
暑熱順化のやり方・始め方
まずは、下の表を使って自分の暑熱順化レベルをチェックしてみましょう。チェックシートで合計点が低い方は、このあとの暑熱順化の方法をチェックして、早めの対策をしましょう。
0点:体が暑さに慣れていない状態。暑くなる前に暑熱順化を!
参照:一般財団法人 日本気象協会 熱中症ゼロへ 「暑熱順化ポイントマニュアル」
無理なくできる暑熱順化の実践方法
- ウォーキングなどの汗をかく運動(1日15~30分、週3~5回)
- 入浴(湯船に浸かる・2日に1回)→ 38~40℃で10~15分が目安
- 軽い筋トレ・ストレッチでの発汗
- 日中に外出する(外気にふれる)機会を意識的に増やす
- 辛い食べ物で汗をかくのもあり
共通して大切なのは、「汗をかくこと」「水分・塩分補給を忘れないこと」「無理をしないこと」です。とくに高齢者は喉の渇きを感じにくくなっているため、定期的な水分補給が大切です。
暑熱順化を始める時期と注意点
では、いつから暑熱順化を始めるのがよいのでしょうか?
答えは、「暑くなる2週間前」からが理想的です。
たとえば、5月の夏日や梅雨明け直後は、熱中症による救急搬送が出現しはじめるタイミングです。早めに順化を始めておくことで、突然の暑さにも体が対応できます。
ただし、暑熱順化の効果は数日間暑さから離れるとリセットされるといわれています。
涼しい日が続いた後や、空調の効いた部屋でばかり過ごしていた後などは、暑熱順化の効果が薄れている可能性があるので注意が必要です。また、高齢者や持病を持っている方は、暑さに弱いため無理のない範囲で行動することが重要です。めまい・頭痛・だるさ・吐き気などがあれば、すぐに涼しい場所で休み、水分・塩分を補給してください。
理学療法士の視点|暑熱順化と身体機能の関係

暑熱順化をスムーズに進めるには、ある程度の心肺機能・筋力・バランス能力が必要です。
歩行やバランスが不安定な方にとって、炎天下での散歩や屋外活動はかえって負担になり思わぬケガにつながることもあります。
そのような方でも安心して取り組める、屋内でできる暑熱順化の方法を以下にご紹介します。
・座ったまま足踏み運動

椅子に座った状態で、太ももをしっかり上げながらその場足踏みを行います。テレビを見ながら、食事の前後などに1~2分を数回でもよいので、軽く汗ばむ程度まで行うことが目安です。
・室内階段や段差を使った昇降運動

ご自宅に階段や小さな段差(10~15cm程度)がある方は、そこを利用してその場で昇り降りする運動を行いましょう。転倒に注意して、手すりなどにつかまりながら1~2段をゆっくり昇降するだけでも、十分な運動量になります。
・掃除や洗濯など、家事作業を活かす

立ちっぱなしや階段の昇降を含むような家事動作は、実は立派な運動です。室内でも、少し息が弾むくらいの家事は、暑熱順化の一環になります。
・ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

シャワーで済ませず、湯船につかって(38~40℃で10~15分程度が目安)じんわりと汗をかくような機会をもちましょう。持病や体調の影響で湯船につかることが難しい場合は、足湯でも構いません。軽い発汗が目安です。入浴後は水分補給も忘れずに行いましょう。
以上のような身体機能に合わせた工夫で、無理なく体を暑さに慣らしていきましょう。
まとめ|熱中症を防ぐ身体づくり
暑熱順化は、「熱中症を防ぐ身体づくり」です。特別な道具や設備は不要ですので、今日から散歩や入浴といった身近な習慣を通じて始められます。
夏を元気に過ごすために、「汗をかく習慣」「こまめな水分補給」「無理しない工夫」を意識しながら、体を少しずつ暑さに慣らしていきましょう。











