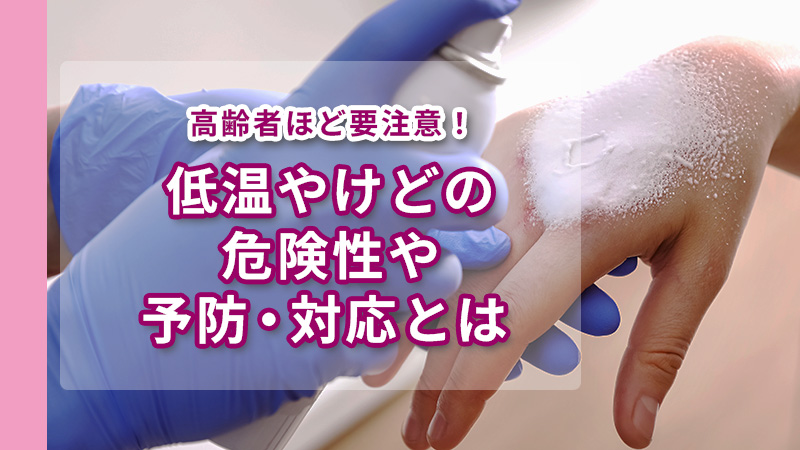
寒い季節に快適な温もりを与えてくれる暖房器具ですが、高齢者にとって「低温やけど(低温熱傷)」は特に注意が必要な事故です。見た目は軽度でも、皮膚の深部まで損傷が及びやすく、重症化しやすいという特徴があります。
本記事では、シニア世代の方々や、そのケアを担当するご家族・介護者の方に向けて、低温やけどを安全に予防するための知識と対処法について解説します。
なぜ高齢者は低温やけどになりやすいのか?

一般的に、低温やけどは約44度から60度程度の「温かくて気持ちがいい」と感じる温度のものに、長時間触れ続けることで発生します。では、なぜ高齢者が若年層よりも低温やけどになりやすいのか、その理由について解説します。
感覚が鈍くなっている
高齢者は、加齢に伴い痛覚が鈍くなっていく傾向があります。そのため、低温やけどの初期症状であるかゆみや痛みに気づきにくく、症状が悪化してから初めて自覚するため、重症化しやすくなります。
さらに、高齢者は若年層と比較して皮膚が薄く、脆弱になっていることも低温やけどのリスクを高める要因となります。特に脚部は、腕などと比べて感覚が鈍くなりやすく、注意が必要です。
寒さを感じやすく、暖房器具を多用する
高齢者は、体温調節機能の低下により寒さを感じやすく、体を温めるためにカイロ、湯たんぽなどの暖房器具や防寒グッズを長時間使用する傾向があります。寒さ対策のために暖房器具を皮膚に直接触れさせたままにしたり、使用中に眠ってしまうことで、低温やけどを引き起こすことがあります。
糖尿病や神経障害の影響
糖尿病を患っている方や末梢神経障害のある方は、より熱さや痛みの感覚が鈍くなるため、低温やけどのリスクが高まります。知覚の低下によって、熱源に接する時間が長くなるため、低温やけどの発症・重症化がしやすくなります。
特に、透析患者や、糖尿病、認知症などで下肢の知覚低下がある方は、湯たんぽや電気アンカの就寝時使用を避けるほうが良いでしょう。
注意すべき暖房器具と具体的な予防策

低温やけどを防ぐためには、暖房器具や湯たんぽなどで、長時間同じ場所を温めないことが最も重要です。そこで、主な暖房器具ごとに、安全な使い方について解説します。
湯たんぽの安全な使い方と注意点
湯たんぽは古くから使用されている暖房器具ですが、低温やけどの原因になりやすい一面もあります。安全に使用するためには、布団を温める目的に限定し、就寝時には取り出すことが大切です。布団が十分に温まったら、湯たんぽを布団の中から出してから眠るようにしましょう。
カイロの正しい使い方
使い捨てカイロは、低温やけどの原因として最も多く報告されている暖房器具のひとつです。そのため、他の暖房器具以上に注意して使用する必要があります。
貼るタイプの使い捨てカイロの安全な使い方は、肌に直接触れないよう、必ず衣類の上から貼ることです。ただし、下着など薄い衣類の上から使用すると、熱が伝わりやすく低温やけどのリスクが高まるため注意が必要です。
また、使い捨てカイロは就寝時に使用を避けることが重要です。特に、ベルトやサポーターなどで押し付けて使用したり、カイロを当てた状態で横になったりする使用法も避けましょう。
電気毛布・電気敷きパッドの危険性と使い方の工夫
電気毛布・電気敷きパッドも低温やけどを起こしやすいアイテムです。他のアイテム同様、就寝時には使用しないようにし、高温で長時間使用しないことが重要です。
電気毛布は、主に布団を温める目的で使用し、布団や体が温まってきたら早めにスイッチを切るか、最低温度に設定しましょう。また、就寝時には電源を切るか、タイマーを1〜2時間で設定し、一晩中の使用することは避けてください。
こたつ・ホットカーペットでの事故を防ぐには
こたつやホットカーペットも、低温やけどの原因となりやすい暖房器具です。これらのアイテムは身体を芯から温かくし眠気を誘うため、使用中は眠り込まないよう注意しましょう。
家族・介護者ができる予防策
高齢者の熱傷事故を防ぐためには、本人だけでなく家族や介護者など周囲の方が日頃から注意を払うことが大切です。
介護者ができる予防策としては、まず皮膚の状態の定期チェックが挙げられます。暖房器具を使用する前後には、低温やけどを起こしていないかこまめに確認し、皮膚の状態に異常があれば早めに医師に相談しましょう。
また、暖房器具の使い方を見直すことも必要です。特に、糖尿病などで神経障害がある方は低温やけどのリスクが高いため、暖房器具を使用する際は、安全に使用できるようサポートしましょう。
症状の見分け方と応急処置

低温やけどの重症化を防ぐためには、早急な処置・対応を行うことが必要です。そこで、低温やけどの症状の見分け方や応急処置のポイントを解説します。
痛みが少ないが、赤み・水ぶくれ・腫れが出ることも
低温やけどの初期症状は、皮膚の赤み (発赤) やヒリヒリした痛み、かゆみなどが現れます。熱さや痛みを感じにくいため、本人が気づかないうちに症状が進行するのが特徴です。
また、症状が進行すると、水ぶくれ (水疱) の出現や皮膚のただれ、腫れなどの症状が現れます。重症の場合は、数日〜1週間ほどして患部の皮膚が黒く変色 (壊死) したり、白く乾燥し、蝋 (ろう) のような質感になったりすることもあります。さらに進行すると、痛みを感じる神経まで破壊されるため、逆に痛みを感じなくなることもあります。
一般的なやけどとの違い
一般的なやけど (高温のやけど) は、熱いものに触れた瞬間に反射的に避けられるため、皮膚の表面に限定されることが多いです。
一方、低温やけどは「熱いと感じない快適な温度」に長時間接触することで、熱の作用が時間をかけて皮膚の深部まで及ぶため、見た目以上に重症化することが珍しくありません。真皮より深い深達性Ⅱ度熱傷やあるいは皮膚全層・皮下組織まで損傷が及ぶⅢ度熱傷となっているケースもあります。
応急処置のポイント
低温やけどに気づいた場合の応急処置の基本は、流水で患部を冷やすことです。患部を冷やすことで、痛みや赤みの症状を軽減し、やけどが深くなるのを防げます。
患部を冷やす場合は、水道水などの流水で10〜30分間を目安に冷やしましょう。ただし、保冷剤や氷を直接患部に当てると、凍傷になるリスクがあるため避けてください。
また、水ぶくれができている場合は、絶対に破らないよう注意しましょう。水ぶくれを潰すと、雑菌が侵入し、症状が悪化するリスクが高まります。
病院に行くべき判断基準
低温やけどは見た目だけでは重症度を判断しづらく、放置すると症状が進行し、皮膚の切除や植皮などの手術が必要になる可能性があります。
もし、「低温やけどかな?」と思ったら、自己判断せず、できるだけ早く医療機関を受診してください。痛みや違和感がある場合はもちろん、赤みや水ぶくれ、皮膚の変色などの症状が現れたら、すぐに医師の診察を受けましょう。
低温やけどの危険性や予防・対応|まとめ
低温やけどは、カイロ、湯たんぽ、電気毛布、こたつといった身近な暖房器具によって、気づかないうちに皮膚の深部に深刻なダメージを与える危険な熱傷です。
高齢者は、痛覚の鈍化、皮膚の脆弱性、そして糖尿病などの合併症により、若年層よりも重症化リスクが非常に高くなります。
低温やけどを予防するためには、長時間同じ部位に熱源を接触させないという原則を守りましょう。例えば、湯たんぽや電気毛布は就寝時に必ず体から離すか電源を切るなど、正しい使用法を徹底することが重要です。ご本人だけでなく、ご家族や介護者が日常的に皮膚の状態を観察し、安全な暖房器具の使い方をサポートすることで、低温やけどの早期発見と重症化予防につながります。
SONOSAKI LIFEでは、健康づくりに役立つ情報や介護の「お悩み」に寄り添う情報をお届けしております。 ほかのコラムもぜひ、ご覧ください。










