
シニア世代は感染症にかかりやすいだけでなく、冬は感染症が流行しやすい季節でもあるため、普段以上に感染症対策が重要になります。しかし、どのような対策を行えばよいのか分からず、結果的に何もしないという方も多いでしょう。本記事では、シニアが感染症にかかりやすい理由や、注意すべき感染症、感染症予防の方法について詳しく解説します。
シニアが感染症にかかりやすい理由

高齢になると、若い頃と比べて感染症にかかりやすくなります。その主な要因は、免疫力の低下です。免疫力は、年齢を重ねるにつれて衰えていき、60歳と20歳の免疫力を比較すると、2倍以上の差があるといわれています。
また、寒さが厳しくなる冬は外出の機会が減り、自宅で過ごす時間が増えます。すると、運動量の減少により、体内にエネルギーが余る状態になるため、食事量が減少することがあります。さらに、運動不足に陥ると身体に蓄積される疲労も少なくなることから、睡眠時間が短くなる傾向があります。
食事量の減少による栄養不足や睡眠時間の減少は、免疫力を低下させる大きな要因です。加齢に加え、こうした要因が重なることで免疫力がさらに低下するため、シニアほど意識して冬の感染症の対策を行いましょう。
シニアが気をつけるべき冬の感染症
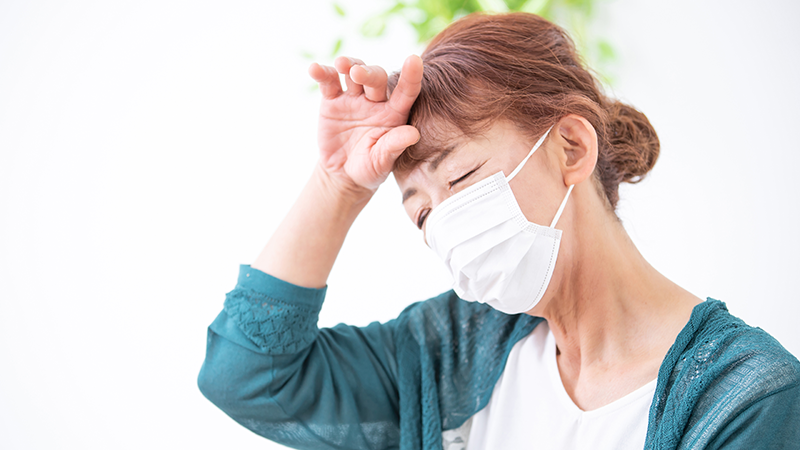
冬の感染症の中には、シニアが感染すると重篤な症状が現れることがあります。ここでは、シニアがかかりやすい主な感染症の中から、特に注意が必要な感染症について解説します。
インフルエンザ
- 原因微生物名:インフルエンザウイルス
- 主な症状:38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛があり、全身の倦怠感など
インフルエンザに高齢者が感染すると完治までの時間が長引いたり、若い人より症状が重くなったりする場合があります。さらに、場合によっては肺炎などの合併症を引き起こす可能性もあるため、特に注意が必要です。
参考:厚生労働省 インフルエンザ(総合ページ)マイコプラズマ肺炎(マイコプラズマ感染症)
- 原因微生物名:肺炎マイコプラズマ
- 主な症状:発熱、全身の倦怠感、頭痛、せきなど
マイコプラズマ肺炎の症状には、発熱などの症状が出始めてから遅れてせきが出るという特徴があります。また、感染者の中には無症状の方も多く、症状の重さには個人差があります。症状が軽い場合、感染していることに気づかないこともあるので、家庭内感染にも注意しましょう。
参考:厚生労働省 マイコプラズマ新型コロナウイルス感染症
- 原因微生物名:新型コロナウイルス
- 主な症状:発熱、せき、倦怠感など
新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザや風邪に似た症状が現れる感染症です。ただし、シニアが感染した場合、重症化しやすく、典型的な症状とは異なる症状が現れることもあるといわれています。
また、検査で陽性反応が出ても症状が現れないケースもあります。新型コロナウイルス感染症には、未解明な部分が多く、想定外の症状や合併症が起こる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
溶連菌感染症
- 原因微生物名:溶血性連鎖球菌
- 主な症状:喉の痛み、発熱、手足の発疹など
溶連菌感染症の症状には風邪に似た症状もありますが、せきや鼻水といった症状が見られない点が特徴です。また、喉が赤く腫れ上がる急性咽頭炎を引き起こす場合もあります。
溶連菌感染症は自然治癒が難しい一方で、抗生剤の服用によって症状が劇的に緩和されます。ただし、症状が治まった後も体内に溶連菌が残ると、リウマチ熱や腎炎を引き起こすおそれがあります。これらの続発症を防ぐためにも、医師の指示に従い、最後まで服薬を続けることが重要です。
感染性胃腸炎(ノロウイルス)
- 原因微生物名:ノロウイルスなど
- 主な症状:嘔吐、腹痛、下痢など
感染性胃腸炎は、細菌やウイルスが体内に侵入することで発症する感染症です。代表的な原因としてノロウイルスがあり、生牡蠣などの食べ物、感染者の嘔吐物、や便などを通して感染します。
感染性胃腸炎は、再感染しやすい特性があるうえに、効果的な治療法がありません。感染源となる細菌やウイルスを体外へ排出することが、唯一の対処法とされています。シニアの場合、嘔吐や下痢が長く続くことで脱水症や喉の窒息といった重篤な症状を引き起こす恐れがあるため、細心の注意が求められます。
介護施設への入居を考えるなら「結核」に要注意
介護施設への入居を考える際に、特に注意が必要な感染症が結核です。結核は、結核菌が体内に侵入することで発症する感染症で、発熱や咳といった風邪に似た症状が現れます。また、結核菌が血液やリンパ液によって全身に運ばれると、肺や脳などに重い症状を引き起こす可能性があります。
参考:厚生労働省 長引く咳や体のだるさに隠れている「結核」を正しく知ろう結核は免疫力の低下によって発症しやすくなるため、高齢者ほど感染・発症のリスクが高まります。さらに、過去に体内に侵入した結核菌が免疫力の低下に伴って再活性化し、発症するケースもあります。このような性質から、結核に感染すると専門的な治療が必要となり、希望する時期に入所できなくなる可能性があるので、結核の新規感染には特に注意しましょう。
今日から始められるシニアの感染症対策

最後に、今日から始められるシニアの感染症対策について解説します。
規則正しい生活をする
シニアの免疫力が低下する要因は、加齢による影響だけではありません。栄養不足や運動不足、睡眠不足といった乱れた生活習慣も、免疫力や体力を低下させる原因となり、感染症にかかりやすい状態を招いてしまいます。
そのため、寒さが厳しい時期でも適度な運動を心がけ、自宅にこもり続けないよう注意しましょう。また、毎日3食しっかりと食べることや、栄養バランスの取れた食事を心がけること、十分な睡眠時間を確保することが大切です。こうしたポイントを意識し、規則正しい生活を通して免疫力を維持しましょう。
手洗い・うがいを徹底する
感染症は、細菌やウイルスが体内に侵入することで発症します。そのため、外出後は手洗いやうがいを徹底し、手や喉に付着した細菌やウイルスを洗い流して、体内への侵入を防ぐことが重要です。
特に、食事前の手洗いは感染性胃腸炎の予防に効果的です。自宅で過ごしている場合でも、食事前には手を洗う習慣を設け、感染症にかかるリスクを大幅に減らしましょう。
かかりつけ医に相談する
感染症対策には、適度な運動などが有効ですが、急に運動をするとケガをするリスクもあります。そこで、かかりつけ医に感染症予防について相談をして、無理なくできる対策を教えてもらうのも良いでしょう。
また、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、特定の感染症には予防接種という予防方法もあります。予防接種を受けると、その感染症に対する免疫力を高められるため、免疫力が低下しやすいシニアほど予防効果が期待できます。
ただし、予防接種を受けることに不安や抵抗感のある方も多いです。そのため、予防接種についてもかかりつけ医へ相談し、必要に応じて接種を検討してみましょう。
定期的に換気・消毒をする
衣類などに付着した細菌やウイルスが自宅内に入り込むと、ずっと空気中に漂っているため、再び手や喉に付着して体内に入り込む可能性があります。そこで、1~2時間ごとに定期的に換気を行い、空気を入れ替えるようにしましょう。
また、ドアノブや手すりなど、複数の人が触れる場所には細菌やウイルスが付着していることがあります。こうした部分は、アルコール ティッシュなどで定期的に消毒し、接触感染のリスクを低減させましょう。
体調の悪い家族とは接触を控える
若い方とシニアの方では、体内の免疫力が異なるため、若い方は軽い症状で済んでも、シニアの方に感染すると重い症状が現れる可能性があります。そのため、少しでも体調が悪い家族とは会うのを控えることがと感染症予防に効果的です。
特に、冬は年末年始など家族が集まるイベントが多く、普段会えない家族とも会える貴重な時期です。そのため、体調が悪くても集まりに参加してしまうことがあるかもしれません。このようなときは、オンラインで集まりに参加したり、窓越しに挨拶だけしたりするなど、直接接触しない方法でコミュニケーションをとりましょう。
シニアが気を付けるべき冬の感染症は? まとめ
シニア世代は免疫力が低下しているため、若い頃よりも感染症にかかりやすくなります。さらに、免疫力が低下していることにより、症状が悪化しやすく、場合によっては命を落とす危険性もあります。
そのため、規則正しい生活習慣を心がけて免疫力の低下を防ぎ、手洗い・うがいの徹底、定期的な換気や消毒などの感染症対策を実践し、冬を元気に乗り越えましょう。
SONOSAKI LIFEでは、健康づくりに役立つ情報や介護の「お悩み」に寄り添う情報をお届けしております。 他のコラムもぜひ、ご覧ください。










