
冬はシニアがうつ症状になりやすい季節
冬は日照時間が短く、寒さも厳しくなるため、屋外で過ごす時間が減りがちです。日照時間の減少による生理的な変化に伴い、「冬季うつ病(季節性感情障害:SAD)」が出やすいと言われています。
「最近、夫(妻)や両親が元気がない」「以前は好きだった趣味にまったく手をつけなくなった」…そんな変化に戸惑う家族も少なくありません。
本記事では、なぜ冬にうつ症状が強まるのか、そして家族がどのように対応するのがよいのかを具体的に解説します。
【原因と特徴】なぜ冬にシニアはうつ傾向が強まるのか

日照時間の短さが脳内物質に影響
冬の短い日照時間が心の健康に大きな影響を与えていることをご存じですか?特に「セロトニン」と呼ばれる脳内物質が減少しやすく、気分の落ち込みや睡眠障害が起こりやすいのが特徴です。この現象は「冬季うつ病(SAD)」と呼ばれ、冬の生活の変化とも密接に関係しています。
セロトニンは心のバランスを保つ重要な物質で、これが不足すると「メラトニン」という睡眠ホルモンのリズムが乱れます。すると、夜眠れなかったり、逆に日中に眠気が強くなったりすることが増えます。シニア層の場合、外出や活動量が減ることもあり、特にこの影響を受けやすいと言えます。
さらに、室内で過ごす時間が長くなる冬は、運動不足や孤独感も加わり、セロトニンの分泌低下を助長します。このため、若年層よりも冬季うつの影響を受けやすいと考えられます。こうした冬特有の環境要因が重なり、心身に大きな負担をもたらしているのです。
シニア特有のうつ症状
シニアのうつ症状は、単に「気分が落ち込む」というものではありません。身体的な不調や認知機能の低下といった形で現れることが多く、家族が認知症と誤解してしまうケースもあります。例えば、頭痛や肩こり、めまいといった症状が前面に出るため、気分の問題とは気づかれにくいのです。
また、記憶力の低下や注意力が散漫になると、「もの忘れ」として認知症と混同されることがあります。ただし、これらの症状は適切な治療やサポートで改善する可能性が高いです。家族は、普段の様子から少しの変化でも気づけるようにしておくことが大切です。
特に、冬季にこれらの症状が顕著になる場合は、専門家の診断を早めに受けることが重要です。「最近元気がない」「趣味に興味を持たなくなった」と感じたら、家族のサポートを始め、必要であれば医療機関に相談しましょう。
【チェックポイント】うつ症状に気づくためのサイン

シニアのうつ症状は、本人が自覚しづらく、家族が最初に気づくケースが多いです。以下の項目に該当するものが多い場合、冬季うつの可能性が考えられます。
- 最近、気分が落ち込むことが多い。
- 夜の睡眠時間が増え、朝起きるのがつらい。
- 日中も眠気が強く、活動する気力が湧かない。
- 炭水化物や甘いものを以前より多く食べるようになった。
- 体重が増加している。
- 外出や人と会うことが億劫になっている。
- 以前楽しんでいた趣味や活動に興味を持てなくなった。
- 疲れやすく、体を動かすのが面倒に感じる。
- 集中力や判断力が低下していると感じる。
- 秋から冬にかけてこれらの症状が現れ、春になると改善する。
これらの兆候が見られたら、「なんだか様子がおかしいな」と思う段階で早めに動くことで、状態悪化を防ぐことができます。
【家族にできること】おすすめな5つの接し方
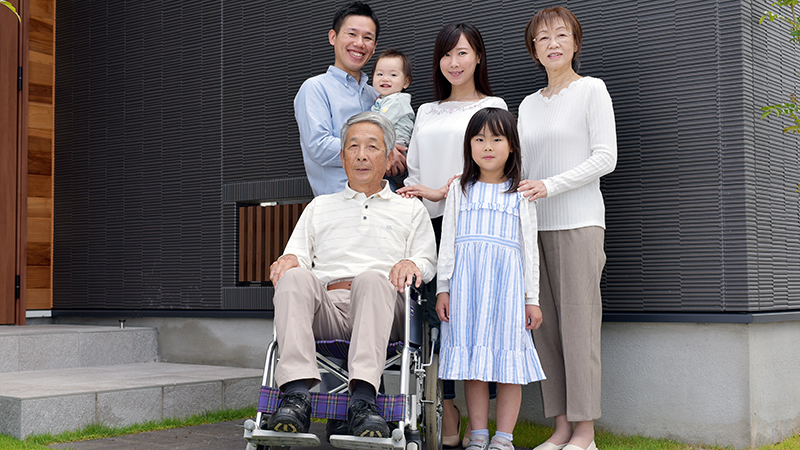
1. 日光を取り入れる環境を整える
朝日を浴びる習慣を促す
朝日を浴びることは、気分を前向きにし、冬季うつの改善に効果的です。朝の光は脳内のセロトニン分泌を促進し、体内時計をリセットする働きがあります。これにより、気分の安定だけでなく、夜の睡眠の質も向上します。家族が積極的に朝日を浴びる環境を作ることで、シニアの生活リズムを整える手助けができます。
具体的には、家族と一緒に朝の散歩を日課にするのがおすすめです。散歩が難しい場合は、ベランダや窓辺で数分間だけでも太陽の光を浴びる時間を確保しましょう。また、朝食を日の当たる場所でとるのも有効です。特に冬は日の出が遅くなりますので、朝日を浴びるタイミングを逃さない工夫が重要です。
室内を明るく保つ
冬は日照時間が短いため、室内を意識的に明るく保つことが重要です。特にセロトニン分泌には光の量が大きく影響します。日光が十分に入らない場合、光療法用のライトを活用するのも一つの手段です。午前中に明るい光を浴びることで、体内時計が整いやすくなります。
具体的には、カーテンを開けてできるだけ自然光を取り入れる工夫をしましょう。さらに、光療法用ライトを取り入れる場合は、2,500~10,000ルクスの明るさのものがおすすめです。それを1日2回、朝と夕方に1~2時間ほど光を浴びるだけでも、気分の改善や集中力の向上に役立つと言われています。
参考:参考:冬季うつへの対処 幸せホルモン(セロトニン)とダークホルモン(メラトニン)を味方につける
2. 規則正しい生活リズムをサポート
睡眠スケジュールの調整
規則正しい生活リズムを保つためには、毎日決まった時間に寝起きすることが基本です。これにより、体内時計がリズムを取り戻し、昼間の活動量が自然と増加します。また、朝の光を浴びることで、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が夜に集中しやすくなります。
具体的には、寝る時間と起きる時間を固定することがポイントです。また、夜に明るい光を浴びすぎると体内時計が乱れるため、就寝前のスマホやテレビの利用を控えるのも有効です。もし昼夜逆転が続いている場合は、少しずつ起床時間を早める形で生活リズムを改善していきましょう。
バランスの取れた食事
冬は炭水化物や甘いものを摂りすぎる傾向があるため、栄養バランスを意識した食事が必要です。これにより、血糖値の急激な変動を防ぎ、気分の安定にもつながります。特にタンパク質やビタミンB群が豊富な食材を取り入れることで、脳内のセロトニン生成をサポートできます。
具体的には、魚、卵、大豆製品、緑黄色野菜を積極的に取り入れるのがおすすめです。また、食事の時間を一定に保つことも重要です。不規則な食事は、体内リズムを乱しやすいため、朝食、昼食、夕食を決まった時間に摂る習慣をつけましょう。
3. 社会的なつながりを維持
孤独感を減らす
冬は寒さや日照不足から外出の頻度が減り、孤独感を抱えやすい季節です。特にシニア層は、家族以外の人との接点が減ることで孤立しがちです。孤独感は、気分の落ち込みや意欲低下を招く要因となるため、家族が積極的にコミュニケーションを図ることが重要です。
具体的には、日常会話を増やすことや、テレビや新聞の話題を共有して、興味を引き出すきっかけを作ることが効果的です。また、趣味や軽い運動などを一緒に行うことで、シニアの生活に活力を取り戻すことが期待できます。家族が共に時間を過ごす姿勢を見せるだけでも、大きな支えとなります。
地域の活動やイベントに参加
地域で行われるシニア向けの活動やイベントは、社会的なつながりを広げる絶好の場です。趣味の集まりや健康教室、ボランティア活動などに参加することで、同年代の人々と交流し、孤立を防ぐことができます。これにより、自分の居場所や役割を感じることができ、精神的な充実感が得られるでしょう。
近隣の公民館やシニアセンターなどをチェックし、定期的に開催されるイベント情報を確認するのがおすすめです。また、家族が参加をサポートすることで、初めての場所でも安心して行動に移せます。こうした活動は、ただ孤独感を減らすだけでなく、健康維持や新しい目標の発見にもつながります。
4. 気持ちを受け止め、無理に励まさない
共感を示す
シニアが気分の落ち込みを抱えている場合、「頑張って」「気にしないで」といった言葉は逆効果になることがあります。本人の気持ちを否定する形になり、余計に孤立感を強めてしまうこともあるため、共感を示す言葉が大切です。「つらいね」「一緒に考えよう」といった寄り添いの姿勢を見せることで、安心感を与えることができます。
また、相手の気持ちに共感する際は、表情や態度にも配慮しましょう。言葉だけでなく、温かい表情や相槌を交えることで、さらに効果的なコミュニケーションが図れます。シニアが「自分は大切にされている」と感じることが、気分の改善につながります。
小さな変化を見逃さない
シニアの気分や行動には、小さな変化が現れることが多く、それを見逃さないことが重要です。たとえば、趣味に対する興味が薄れたり、食事量や睡眠パターンが変わったりすることが兆候となる場合があります。こうした変化を早期に察知することで、必要な対応が取れるようになります。
日常生活の中で気になる変化が見られた場合、家族でその内容を共有し、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。また、変化を記録しておくことで、医療機関での診断にも役立ちます。細かな観察と行動が、シニアの心身の健康を守る鍵となります。
5. 専門的なサポートを活用
医療機関への相談
冬季うつが重症化している場合や改善が見られない場合は、精神科や心療内科などの専門医を受診することが必要です。医師の診断により、適切な治療が選ばれることで、回復の可能性が高まります。特にシニアの場合、うつ症状が認知症と混同されやすいため、専門的な評価が欠かせません。
受診をスムーズにするためには、家族が同伴し、症状の経過や生活習慣の変化を説明することが役立ちます。例えば、いつからどのような症状が現れたのか、どんな場面で悪化するのかを事前にメモしておくと良いでしょう。医療機関での適切な対応が、シニアの心身の健康を取り戻す第一歩となります。
カウンセリングや心理療法
医療機関の治療に加え、カウンセリングや心理療法も効果的です。専門家との対話を通じて、自分の気持ちを整理したり、ストレスへの対処法を学んだりすることが可能です。これにより、気分の改善や不安感の軽減が期待できます。
【医療機関の活用】早めの受診で適切な対応を

専門的なサポートを検討
うつ症状が長引く場合、専門の医療機関(精神科・心療内科)への受診が必要です。特にシニアの場合、うつと認知症の鑑別が求められることも多く、専門的な診断なしには正しい治療法が選べません。
受診サポートのコツ
家族が同伴する
診察時に家族が同伴することは、シニア本人にとって大きな安心感を与えるだけでなく、診断や治療方針を正しく理解する助けになります。医師の説明は専門的な内容が多く、一人で聞き取るのが難しい場合があります。そのため、家族がサポート役として同席し、必要に応じてメモを取ることが重要です。
また、家族が同伴することで、本人が伝えきれない細かな症状や行動の変化を医師に補足説明できます。例えば、普段の生活で見られる小さな変化や、本人が認識していない症状を医師に伝えることで、より正確な診断につながります。同席は、治療を進める上で重要な「チーム」としての役割を果たすことになります。
事前準備
受診前に症状や生活習慣の変化を整理しておくことも、診断をスムーズに進めるための重要なポイントです。症状がいつから現れたのか、どのような場面で強くなるのか、日常生活にどんな影響を与えているのかを具体的に記録しましょう。これにより、医師が正確に状態を把握しやすくなります。
例えば、「食欲が減退した」「夜中に何度も目が覚める」「趣味への興味を失った」といった詳細な変化をリスト化しておくと役立ちます。また、普段の服薬状況や既往歴についても、可能であれば情報をまとめておきましょう。こうした準備が、診察時間を有効に活用する鍵となります。
相談先に迷ったら…
地域包括支援センターや精神保健福祉センター
うつ症状に関する相談は、地域包括支援センターや精神保健福祉センターといった公的機関を活用することができます。これらの窓口では、専門のスタッフが対応し、必要に応じて具体的な支援や医療機関への紹介を行ってくれます。初めての相談でも親身に話を聞いてくれるため、気軽に利用することができます。
また、これらの機関では、地域に密着したサポートを提供しているため、相談者に合った解決策を提案してもらえることが特徴です。電話や直接訪問で相談できる場合が多いため、迷ったときはまずこうした窓口に連絡してみるとよいでしょう。地域の公的支援は、身近で利用しやすい選択肢の一つです。
かかりつけ医からの紹介
既に信頼しているかかりつけ医がいる場合、その医師に相談するのもおすすめです。かかりつけ医は、日頃の健康状態を把握しているため、症状の背景や変化を理解しやすい立場にあります。さらに、必要な場合は適切な専門医への紹介状を作成してくれるため、スムーズに専門的な診察を受けることができます。
紹介状を持参することで、専門医での診察もスムーズに進むことが期待されます。また、かかりつけ医が治療後も継続的にフォローアップを行ってくれる場合が多いので、相談の継続性を確保できるというメリットがあります。まずは気軽に話せる存在として、かかりつけ医を頼ってみるのも良いでしょう。
【家族のケア】サポートする側も疲れない工夫を

サポートする家族が精神的・身体的に疲れきってしまうと、双方にとって悪循環です。
家族自身の休息・リフレッシュ
家族がサポートに全力を注ぐあまり、精神的・身体的に疲れきってしまうことは少なくありません。この状態が続くと、家族自身の健康が損なわれ、結果的に適切な支援が難しくなるという悪循環に陥ります。サポートを続けるためにも、家族自身が休息を取ることが必要です。一人で抱え込まず、気持ちや負担を分かち合う工夫が重要です。
具体的には、親戚や友人、信頼できる人に相談するだけでも気持ちが軽くなることがあります。また、カウンセラーや支援団体を利用して話を聞いてもらうのも良い方法です。さらに、短時間でも自分の趣味やリフレッシュできる時間を確保することで、心の余裕を保つことができます。例えば、15分程度の散歩や読書、好きな音楽を聴くといったシンプルな活動から始めてみましょう。
情報共有と分担
家族内で役割を分担することも、サポートを無理なく続けるための鍵です。一人が全ての負担を背負ってしまうと、長期的に見て心身の疲労が蓄積し、サポートの質が低下する恐れがあります。そのため、家族全員で状況を共有し、可能な範囲で手助けを分担する体制を作りましょう。
具体的には、誰がどの時間に何を担当するかを明確にするのがポイントです。例えば、食事の準備や買い物、通院の付き添いなど、具体的なタスクをリスト化し、それぞれの得意分野や時間的余裕に応じて割り振ります。また、家庭内での情報共有には、カレンダーやメモを活用するのも効果的です。このように、家族全体で協力する仕組みを作ることで、支援の負担を軽減することができます。
【まとめ】家族の理解と専門サポートで回復を目指そう
冬は日照不足や寒さなどの影響で、シニアのうつ症状が表面化しやすい時期です。気分の落ち込みや興味・意欲の低下、身体的不調などが見られたら、家族は「頑張れ」と励ますのではなく、まずは共感と受容を示し、安心できる環境を整えてあげてください。
必要に応じて、医療機関や公的支援機関を積極的に活用することで、早期の改善が見込めます。家族が理解し、無理のないサポートを続けることが、シニア本人の回復への大きな一歩となるのです。













