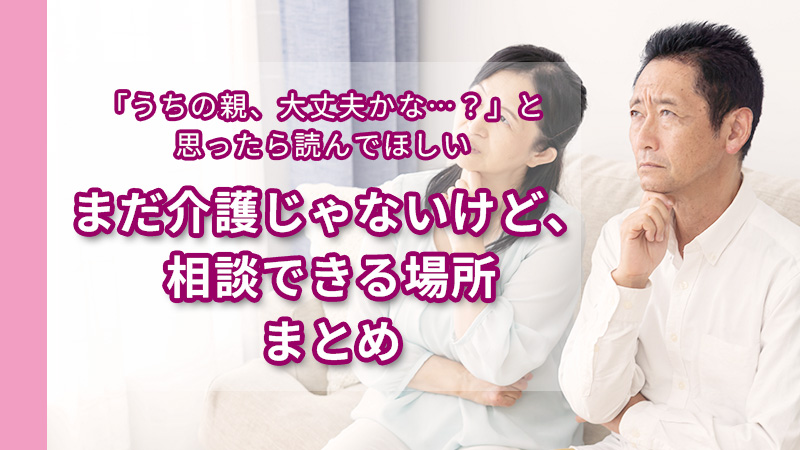
両親の体調や生活に変化を感じ、「まだ介護というほどではないけれど、この先どうなるのだろう?」と漠然とした不安を感じる方は少なくありません。特に、自分自身も年齢を重ねる中で、両親の健康や暮らしに対する心配が増すことは自然なことです。
本記事では、高齢になった両親のことを相談できる場所を中心に、相談する大切さについて解説します。「うちの親、大丈夫かな?」と感じた気持ちこそが、大切な「介活(介護のための準備)」の第一歩です。早い段階から相談先を知り、必要な情報を得ておくことで、将来への備えが可能になります。
親のこと、誰に相談したらいいの?

両親の変化に気づいても、「家族に直接伝えるのは難しい」「それほど深刻ではない」と感じ、一人で抱え込んでしまうことがよくあります。コミュニケーションが取りづらくなるなど、接する中でストレスが蓄積し、気持ちが沈んでしまうこともあります。
こうした状況を避けるためには、一人で全てを抱え込まず、相談できる相手を確保することが重要です。第三者から客観的なアドバイスを得ることで視野が広がり、少しずつ心の余裕も生まれます。また、介護が必要な状態でなくても、事前に話し合っておくことで、今後の道筋が分かり精神的な安定につながります。
相談できる場所はこんなにある

両親の状態や不安について相談できるのは、兄弟や友人だけとは限りません。介護や老いに関することを相談できる公的な場所は、多数存在します。そこで、どのような場所を活用すると良いのか、信頼できる相談先を紹介します。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、市町村が主体となり、地域住民の健康保持と生活の安定を包括的に支援することを目的としています。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が配置されており、高齢者の生活を多角的にサポートしています。 地域包括支援センターでは、地域の高齢者や家族・介護者に対し、初期段階から継続的・専門的に相談支援を行っています。高齢者とその家族を、地域の多様なサービスにつなげてくれるので、介護が必要になる前の段階から支援を受けることが可能です。介護開始後も含め、継続的に頼れる窓口として機能しています。
家族のかかりつけ医
両親の健康状態に一番詳しいのは、やはりかかりつけ医です。身体的な衰えや認知症の初期症状など、異変に気づいたときは、まずかかりつけ医に相談してみましょう。
さらに、介護保険の要介護認定を受ける場合、主治医の意見書が必須となります。介護サービスの必要性を感じたら、前もって相談しておくことが望ましいです。
また、高齢者は家族の助言よりも、医師の言葉に耳を傾ける傾向があります。介護保険の申請やサービス利用について説得するときは、医師からも勧めてもらうのが効果的です。
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進する非営利組織です。地域住民、民生委員、社会福祉施設、保健・医療・教育関係者などが協力し、「福祉のまちづくり」を目的として活動しています。
また、市区町村の社会福祉協議会は、在宅介護支援サービスや地域福祉の活動拠点としての役割を担っています。都道府県の社会福祉協議会では、認知症や知的障害などに不安を感じている方を対象とした「日常生活自立支援事業」や福祉サービスの苦情相談なども実施しています。介護に関する幅広い相談に対応しているので、気軽に相談してみましょう。
市区町村の福祉相談窓口
市区町村は介護保険の保険者であり、地域包括ケアシステムの構築責任を担っています。そのため、地域住民の心身の健康保持や生活の安定を包括的に支援するための各種施策を展開しています。
地域ごとに施策は異なりますが、中には独自の介護相談窓口を設けていることがあります。この窓口では、介護保険制度に関する情報提供や在宅介護に関する相談対応、具体的なアドバイス、必要な介護サービスへの仲介役等を行っています。解決までの道のりを示してくれるので、介護に関する不安が大きい場合には有効な相談先となります。
民生委員
民生委員は、地域の福祉に関する情報収集や相談支援を担う役割を持つ公的な協力者です。地域住民が自立した生活ができるよう必要に応じて支援をしており、自宅介護が必要になった場合の相談にも応じています。
具体的には、地域の介護サービスに関する情報提供、介護支援専門員の紹介、訪問による状況確認などを行います。相談を希望する場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせ、民生委員へ相談してみましょう。
高齢者支援の民間サービス
公的な相談窓口やサービスに加えて、 高齢者支援の民間サービス も、高齢になった両親との生活を支える選択肢となります。 これらのサービスでは、介護保険の対象外となる支援や、より専門的な支援を提供していることが一般的です。
また、弁護士や司法書士といった専門家が在籍している場合、財産管理や将来の相続、認知症に備える家族信託、任意後見制度など、法的な側面からの支援も相談できます。
民間サービスでは費用がかかりますが、公的サービスだけでは対応しきれないニーズにも柔軟に対応しているので、複雑な事案や迅速な対応が必要な場面において、有効な支援手段となります。
介護経験者のコミュニティ
両親の介護に直面する中で、「自分だけがこんなに辛いのか」と感じることは少なくありません。そんな時、同じような経験を持つ人々とつながれるコミュニティは、大きな心の支えとなります。
オンラインの掲示板などでは、多くの介護経験者が自身の苦労や感情を共有し、互いに励まし合っています。また、「認知症カフェ」や「家族の会」といった場では、対面で経験を共有し、実践的な情報やアドバイスを得ることも可能です。介護ストレスや孤独感を軽減するために、ぜひこれらのコミュニティも活用してみてください。
相談しても「何もなかった」で大丈夫

「相談したけれど、特に問題はなかった」「心配しすぎだったかもしれない」と感じることもあるかもしれません。しかし、相談したこと自体が無駄になることはありません。
相談を通じて地域の支援体制や利用できるサービスについて知っておけば、「何かあったときにすぐ相談できる」という安心感が生まれます。また、不安な気持ちを誰かに話すことで、心理的な負担やストレスが軽減され、あなたの心の健康維持につながります。
あなたが不安を感じた「今」がタイミングです

「介護は突然やってくる」と言われることが多く、両親の介護期間は平均で約5年、中には5年を超えるケースも約半数に上り、長期にわたる傾向にあります。しかし、要介護認定や支援が必要になると、介護者の精神的な余裕がなくなり、適切な判断や準備が困難になることがあります。
だからこそ、あなたが両親の変化に「あれ?」と気づいた「今」が、まさに準備を始める最適なタイミングです。両親が元気なうちに、将来の希望や介護の方針について話し合い、資産状況を確認しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
まとめ|「ちょっと相談」から始めてみませんか?
両親の老後のことやご自身の負担に関する不安を一人で抱え込まず、今回ご紹介した相談先に「ちょっと相談」することから始めましょう。
介護は「お世話」だけでなく、制度や支援を活用した「マネジメント」という視点も大切です。一人で全てを背負い込むのではなく、人や仕組み・制度を利用することが、無理のない介護につながります。早い段階で情報を得て、これからを考えておくことで、両親の心身の状態悪化を防ぎ、あなた自身の「介活」を計画的に進めることができるでしょう。
SONOSAKI LIFEでは、健康づくりに役立つ情報や介護の「お悩み」に寄り添う情報をお届けしております。 ほかのコラムもぜひ、ご覧ください。










