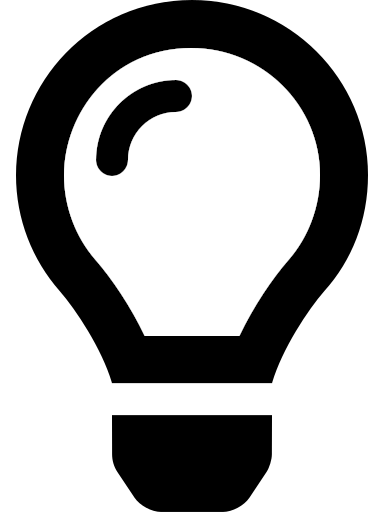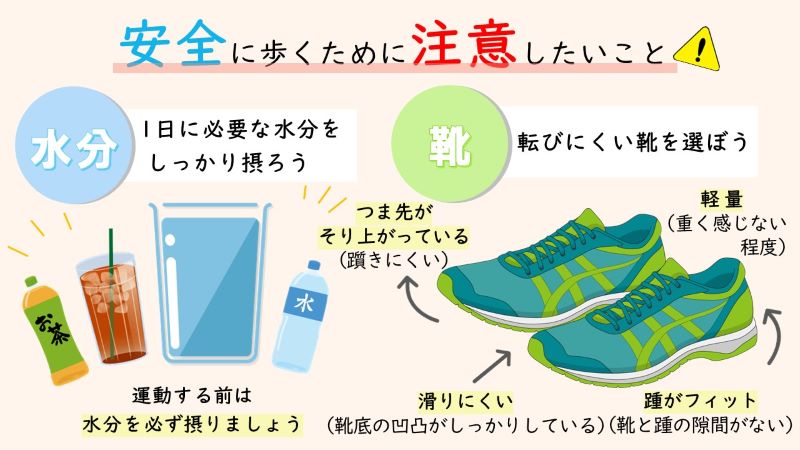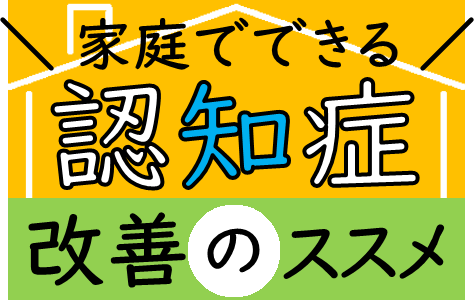高齢な方が肺炎などで数週間寝込んでしまうことで、スムーズに歩けなくなることがあります。
その理由として「足の筋肉が落ちたため」と言われることがよくありますが、実は「歩き方を忘れた」というケースが多いのはご存じでしょうか?
認知症であれば「歩行」を中心とした運動は、症状改善のために欠かせないこととなります。
今回の記事では、「歩行」のメカニズムと、歩けなくなった高齢者が再び歩けるための練習法について解説していきます。
脳が歩き方を忘れる理由
高齢者は病気やケガなどで長期間歩かなくなると、「歩くために体をどう動かせばいいか」を脳が忘れてしまうことがあります。つまり、「歩き方」を忘れてしまうのです。
失敗しながら習得する動作
人間の「歩く」「食べる」「話す」などの動作は、生まれたときには当然できません。
成長の過程で何度も失敗しながら、繰り返し覚えてその動作を習得していきます。
自転車の乗り方やピアノの弾き方、逆上がりや縄跳びなども同様で、複雑な動作を何度も練習・学習することで身に付けていきます。
しかし、学習して身に着けた動作は、ある期間行っていないと忘れてしまいます。

脳が動作を忘れてしまう
例えば自転車に何年も乗らずにいたとしましょう。
久しぶりに乗ってペダルをこぐと、最初はバランスが取れずにフラフラしますが、しだいに滑らかに自転車を扱えるようになります。
これは、自転車に乗るという脳の記録回路が最初はうまく作動しなかったが、しばらくすると徐々に体の使い方を思い出したということです。
地域の運動会で大人がリレーをすると転ぶ姿をみかけないでしょうか。これもしばらく走っていない人が急に全速力で走ったため、脳が体の動かし方を思い出せずに、足がもつれてしまう現象だといえます。
「歩く」動作も歩いていないと忘れてしまう
「歩く」という動作は足を動かし、手を振って、多くの筋肉を動かして全身をコントロールしています。
視覚から得られる情報や足底の感覚、体の傾きなどを瞬時に判断してスピード調整や全身のバランスをとっているのです。
しかし、しばらく歩いていないと、細やかで瞬時に判断していた動作を忘れてしまい、結果うまく歩けなくなってしまうのです。
歩き方を思い出す
歩き方を忘れたならば、思い出すことで再び歩くことができるようになります。
何年も車いすで歩いていなくても、歩く練習を重ねて「歩き方を思い出す」ことで歩行を再獲得できる可能性があるのです。
人間の体は繰り返し動かしていけば動作が滑らかになり、逆に動かさなければその動作はぎこちなくなります。
「歩く」ことも同じで、歩く練習を積み重ねていけば上達する動作となります。