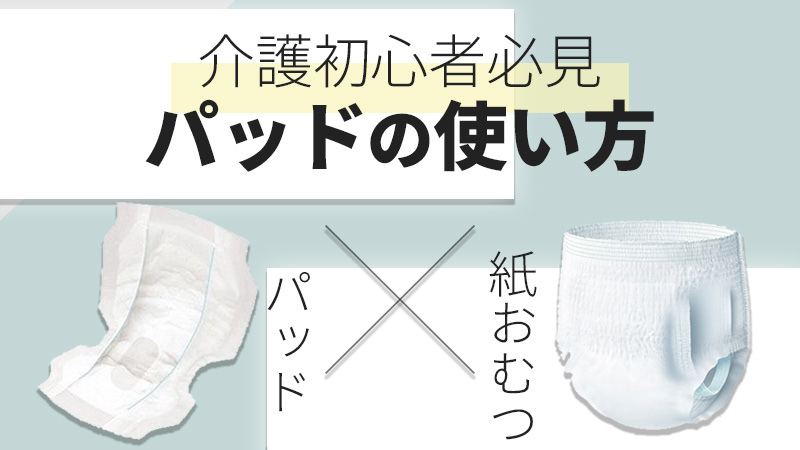
尿とりパッドは、下着などに装着するだけで使える、高齢者の排泄ケア用アイテムのひとつです。
パッドだけでも十分利用できますが、排尿量が多い方には、紙おむつと併用して吸収量を増やす方法もあります。
一方で、紙おむつよりも専門的なイメージがあるため、パッドの特徴や適切な使い方を知らない方も多いかもしれません。
本記事では、尿とりパッドの特徴、紙おむつとの併用方法、メリット、おすすめのパッドについて詳しく紹介します。
排尿量の多さによるトラブルでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
排泄ケアに使われる尿とりパッドとは

尿とりパッドは、高齢者の排泄ケアには欠かせないアイテムですが、その詳細を知らない方も多いようです。
パッドのみを下着に取り付けての使用はもちろん、さらには紙おむつと併用することで、より多くのシーンで活用できることをご存知でしょうか?
ここでは、尿とりパッドの理解を深めるために、主な特徴と紙おむつとの併用の目的について解説します。
尿を吸い取るインナー部分のこと
尿とりパッドとは、失禁用下着や紙パンツなどに設置して使用する、 尿を吸収する機能を備えた アイテムです。 紙おむつとは異なり、パッドだけでは下着の代わりとして使用できません。 そのため、尿を吸収する機能のない下着に取り付けることで、下着に紙おむつと同様の機能を持たせるといった活用法があります。
紙おむつと併用する目的
尿とりパッドの使い方の一つに、紙おむつの中にパッドを取り付けて併用する方法があります。
しかし、紙おむつ自体にも吸収体が装着されているため、尿とりパッドを併用する必要がないと考える方も多いでしょう。
紙おむつと尿とりパッドを併用する目的は、 尿の吸収量を増やすこと です。
例えば、排尿量が多い場合、紙おむつだけではすべての尿を吸収できず漏れてしまうことがあります。
このような時にパッドを併用すると尿を吸収できる量が増えるため、紙おむつから漏れにくくなり、尿でベッドなどを汚すリスクの軽減につながります。
紙おむつと尿とりパッドを併用する使い方

尿とりパッドは、紙おむつの着用方法に合わせて「パンツタイプ」と「テープタイプ」の2種類があります。 ここでは、タイプごとに紙おむつと併用する使い方を解説していきます。
パンツタイプの使い方
パンツタイプの尿とりパッドを紙おむつと併用するときは、次の手順に従って着用します。
- 紙おむつに両足を通す
- 紙おむつを膝下まで上げる
- 足を左右に開き、尿とりパッドを装着する
- 最後まで履く
パンツタイプを上手に着用するポイントは、 紙おむつ内の立体ギャザーをつぶさないこと です。 立体ギャザーからパッドがはみ出していると尿が漏れるリスクが高まるため、きちんとギャザー内に収まるように装着しましょう。
テープタイプの使い方
パンツタイプの尿とりパッドを併用するときは、次の手順に従って着用します。
- テープタイプの紙おむつを左右に2~3回伸ばす
- 紙おむつの立体ギャザーの内側に、尿とりパッドを入れる
- 装着者の身体を横向きにし、おむつの中心と鎖骨の位置を合わせる
- 身体をゆっくりと仰向けに倒し、尿とりパッドを装着する
- 紙おむつを引き上げ、立体ギャザーの位置を調節する
- 紙おむつを装着する
また、パンツタイプの紙おむつとテープタイプの尿とりパッドを併用する場合は、 先にベッド上で尿とりパッドを取り付けてから 紙おむつを装着します。 紙おむつを装着する途中でパッドを取り付ける手順ではないので、注意しましょう。
尿とりパッドを併用するメリット

尿とりパッドを使うメリットには、次のようなことが挙げられます。
- 介護負担の軽減
- 紙おむつ代の節約
尿とりパッドと紙おむつを併用する場合、パッドだけで尿を全て吸収できれば 紙おむつを交換する必要がなくなります 。
尿とりパッドの交換だけで排泄ケアが済むので、介護負担の軽減や紙おむつ代の節約といったメリットにつながるのです。
ただし、紙おむつが尿で汚れていなくても、蒸れなどによって雑菌が繁殖している可能性があります。
尿とりパッドを使っていて汚れが見えなくても、 紙おむつは定期的に交換するようにしましょう 。
尿とりパッドを使うときの注意点
尿の吸収量を高めるためには、尿とりパッドを重ねて装着するのが有効だと思うかもしれません。
しかし、一般的な尿とりパッドは、反対面に防水シートが使われていることで漏れない設計になっています。
そのため、パッドを重ねても 下側のパッドが尿を吸収することはありません 。
尿とりパッド以上に吸収量を増やしたい場合は、補助パッドを活用しましょう。
最適な尿とりパッドを選ぶための3つのポイント

尿とりパッドは便利なアイテムである一方、装着者によって最適なパッドは異なります。 そこで、最適な尿とりパッドを選ぶためにチェックしておきたいポイントを解説します。
1.吸収量
尿とりパッドの吸収量は商品によって異なり、一度の排尿量も人それぞれです。
そのため、装着者の排尿量や装着時間に応じて、 適切な吸収量の尿とりパッドを選ぶ ことが大切です。
さらに、歩行能力やトイレでの排泄が可能かどうかも考慮すると、より本人の状態に合ったパッドを選びやすくなります。
また、感染症を防ぐために、尿とりパッドは汚れていなくても定期的に交換する必要があります。
吸収量が多いからといって付けっぱなしにすることはできないので、 過不足のない吸収量のパッド を選びましょう。
2.通気性
紙おむつと尿とりパッドを併用すると、おむつ内の湿度が高まり蒸れやすくなります 。
尿漏れを防ぐためには有効ですが、不快感から大きなストレスを抱いてしまうことがあります。
さらに、おむつ内の蒸れは肌トラブルの原因にもなるので、十分に注意しなければなりません。
そのため、尿とりパッドの通気性は大切なチェックポイントです。
特に、就寝用のパッドや、日頃からベッド上で過ごす時間が多い方のためのパッド選びでは、十分な通気性が確保されているかを確認しましょう。
3.消臭性
パッドに吸収された尿のニオイが残ってしまうと、 本人や周囲の人に強い不快感を与えます 。
特に、就寝時や外出時など、すぐにパッドを交換できない場合は、尿のニオイがより気になることがあります。
そのため、尿とりパッドに消臭機能が付いているかどうかも確認しておきましょう。
消臭機能があると、パッドだけでニオイケアができるため、利用できるシーンがグッと増えます。
装着者本人の抵抗感も軽減されるので、尿とりパッドをより便利に活用できるようになります。













